その論文が自分にとって有益なものかどうかを判断する方法があります!
PICOをまとめる作業は時間がかかりすぎるので最近は意識していません。
それは、以下の手順です!
①論文を読み始める前にその雑誌のインパクトファクターを調べて読むに値するかどうか判断する
②イントロダクションの最後の1文を読んで研究の目的を理解する
③ディスカッションの最初の1文を読んで研究によって導き出された結果を知る。
すこし、解説していきます。
目次
①インパクトファクターを調べて読むに値するかどうか判断する:「無名の雑誌の論文を読むのは人生の無駄!」
私は以前恩師から「無名の雑誌の論文を読むのは人生の無駄」と言われたことがありますが、雑誌は非常にピンキリです。
New England Journal of MedicineやLancet, JAMAなど非常に格式が高い雑誌もあれば、お金を払えば掲載してくれるような雑誌があります。
それらの雑誌の権威が分かるのがインパクトファクターです。
論文を書く際には、研究の穴がない様に、過去の論文の研究法と矛盾がないか、集団の選択が適切だったかなどなどに注意をはらい、臨床的な価値や新規性を最大限に引き出すことができているかを考え、練っては作り直し練っては作り直しの作業をしていきます。
そして、自分の研究を多くの人に役立てて欲しいため、多くの人の目に留まるように権威のある雑誌から投稿していきます。
つまり、基本的には、インパクトファクターが高い雑誌から投稿するわけです。
ただし、いい雑誌の査読の目は非常に厳しく、十分な価値や新規性がなかったり、研究の設計が不十分であるとすぐに落とされます。
例えば、循環器領域で権威のあるCirculationはインパクトファクター22.4で採択率は8%です。
日本循環器学会の雑誌であるCirculation Journal はインパクトファクター2.9で循環器領域の54/128位と真ん中程度のランクの雑誌ですが、それでも採択率は25%程度と低いです。
よってインパクトファクターが極端に低い雑誌に載っている論文は極端に大きな穴がある可能性があります。
私はインパクトファクターが1点にも満たない雑誌は、はなから読まないことが多いです。
ましてや査読を通ってないような論文は論外です。
②イントロダクションの最後の1文を読んで研究の目的を理解する
され、それでは手にした論文に権威性がある事が分かり、実際に読み始める時に、自分の求める内容の研究であるかを判断するための1行があります。
それは、実は、イントロダクションの最後の1文です。
イントロダクションの最後の段落は決まって研究の目的が書かれています。そして、それはパラグラフの形成上最後の文に書かれることが多いです。
その研究の研究が何を明らかにするためのものかが、自分の持っている疑問と似ているのであれば読む価値がありますね。
③ディスカッションの最初の1文を読んで研究によって導き出された結果を知る。
そして、次はその研究の目的を遂行し得られた結果を確認しましょう!答えが書いてあります。
それは、実は、ディスカッションの最初の1文です。
ここには、その研究で明らかにされた主な結果をダイジェストされている事が多いです。よって、その、研究の大事な結果が最もまとめられた形で書いてあります。
論文にはいくつかお作法があります。メソッドをどこまで詳しく書くか、リザルトの書き方、引用の書き方などなどありますが、
「イントロダクションの最後の段落はその研究の目的を明記すること」と
「ディスカッションの最初はその研究の結果のダイジェストを書く事」も立派なお作法です。
よって、論文の書き手は、食事のマナーと同じように、論文のマナーも守って書いていくわけです。
もし、このマナーが守れていない論文があれば、すぐに内容が理解できないため、非常に読みにくいです。
要するに雑誌に投稿した際には査読者にいら立ちを与えかねません。よって、ある程度知っている書き手はきちんとマナーを守って書くわけです。
インパクトファクターがある低い論文で、このマナーが守れていない論文は研究にふなれな書き手によるもので、穴が多く読むに値しない研究かもしれません。
まとめ
日常臨床での疑問点の解決方を探す際、論文を書く際など、多くの論文の中から自分が求める情報を探し出す必要がありますが、論文は無限に出てきますので、1つ1つすべて読んでいく事はできません。
検索方法のコツなどもありますが、今回は、私が一番重宝している論文の内容を瞬時に判断するコツを共有させてもらいました。 検索方法のコツなども今後共有していきたいと思います。
フォローしてね♪
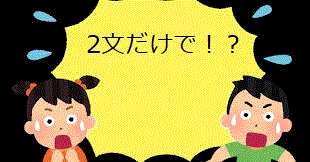









私は原著論文を5本書き、現在も4本執筆中で何千時間も論文を書くことに時間を費やしてきました。その結果見出した論文を読むコツについて共有したいと思います。