目次
特許と弁理士
特許の必要性
開発中のアプリの特許を申請するか迷いましたが念のため申請することにしました。
この辺の考え方が人によって国民性によって異なる事かもしれません。
私が、アプリ開発で受けた講義はイギリス人が行うもので、
「特許申請にかかる時間を費やすよりも早くアプリを世に出して、先行者利益を得るべし。
特許でノウハウを出し惜しみするのではなく、ノウハウは皆で共有すべき。」
というような考えでした。
そういうものだと思ってもいましたが、どうやら日本では少し違うように思いました。
日本ではアイディアや技術に価値がおかれているのか、みなパクられるのを恐れますし、パクろうとする文化もある気がします。
申請から審査にも迅速でお願いすれば、そこまで時間も要しないようです。
早期審査で2か月だとか。ふつうは1年ほどかかるようです。
知人で会社の特許を担当しているものに相談したところ、特許を持っていること自体が守りにもなるし、ブランドのアピールにもあるとのこと。
私が作るアプリは、医療界で画期的なものになる(はず。そうだと信じています)ので、特許を申請することにしました。
頼む人は=弁理士さん。どうやって見つける?
さて、といっても特許ってどうやってとるのでしょうか?
それを専門にしている人たちは弁理士という資格を持った人たちです。
特許を申請する時の書類を作成し、特許庁から意義があったときに、その弁解を行ってくれます。
一般的には1件の特許で合わせて80万~100万円ほど費用が掛かるのが相場のようです。
私の場合は、まずは、経済産業省のInnoHubという取り組みで、弁理士を紹介してもらいました。
2024年4月30日現在は、相談の受付を一時休止となっており、2024年6月上旬に再開予定のようです。
この取り組みにて、知財戦略などに関する専門家につないでもらうことができました。
そこで税理士の方を紹介され、親身な方でInnoHub経由だと格安で対応されているとのことでした。
もう1人弁理士の方に話を聞きました。
知人からの紹介です。やはり、知人からの評価が高いことは、なかなか判断基準が分からない新しいことをやるうえで、非常に重要で、もしかすると唯一信頼できる?、情報です
こちらの方は相場通りの価格。
結局、私はInnoHubから紹介を受けた方を選びました。
理由は
①経歴や実績がしっかりある事
②話してみて持った印象が良かったこと。適時適切な質問をしてくれること
③安いこと
今後の予定について
アプリの概要について説明しました。
まずはこちらで新規性や将来性について考えをまとめます。
その後、税理士事務所が1か月ほどで初稿納品。
その後、1か月ほどの間に書類チェック会を経て、納品予定です。
祝!3カ月コースの初顧客獲得!
今日は、5月から始める予定の3か月の医学教育のコースのメンバー集めも行いました。
現在興味を持ってくれている人が4人。
さらに5月7日に文京区でセミナーを開催予定であり、そこで集客しセールスを行う予定。
セミナーについてはスライドを作成した。18枚ほど。
うまくセールスにつなげたいです。
興味をすでに持ってもらっている人にはLINEで個別にセールスします。
前身の地域貢献活動の参加者の感想をまとめて、後押しになるような資料を作りました。
こんな感じにCanvaで作りました。

LINEで個別にその人だけに刺さるように文章を書きました。
ここで思ったのが、その人の情報は知っていれば知っているほど、いいという事。
どんな趣味を持っているか、どんな持病があるか、どんな不安を持っているか。
その人が困っている自分の顔を、提供するサービスを通して、その人の笑顔に変わることを想像させることがセールストークだと思っています。
だから、どうすれば笑顔になるのか。それを知っていることが非常に重要だと思います
結果、今の時点で1人から返信があり、
1人契約お申込み!!!
1人目のクライアントです。
大切にしよう。
祝、初クライアント!
妻を役員に
奥さんを役員(取締役)に向か入れました。
守備力が強い奥さんに会社の経営に携わってもらうことにしました。
そのために株主総会を開き、登記の変更が必要でした。
登記は郵送で処理できるようなので、そのようにしました。
フォローしてね♪
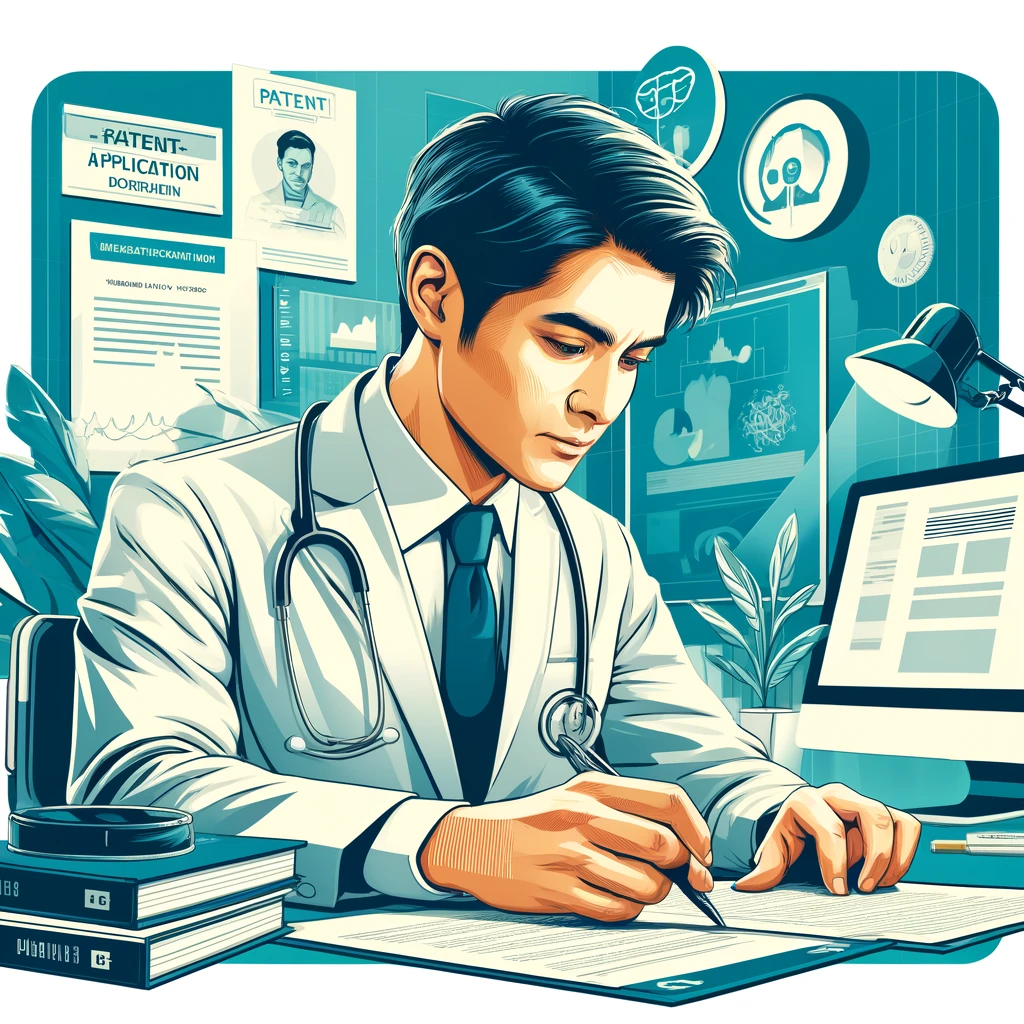














コメントを残す